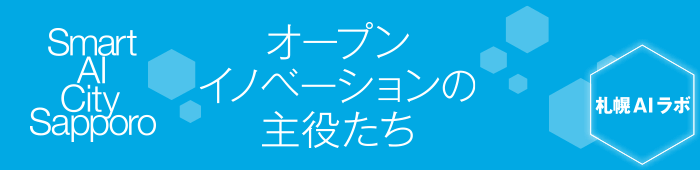 北海道大学 大学院情報科学研究院 調和系工学研究室 教授 川村 秀憲
北海道大学 大学院情報科学研究院 調和系工学研究室 教授 川村 秀憲
2020年3月1日 公開
社会と調和するAI技術を追求していく
産学官連携による札幌AIラボを率いて、世界に誇れる技術集積を目指す。
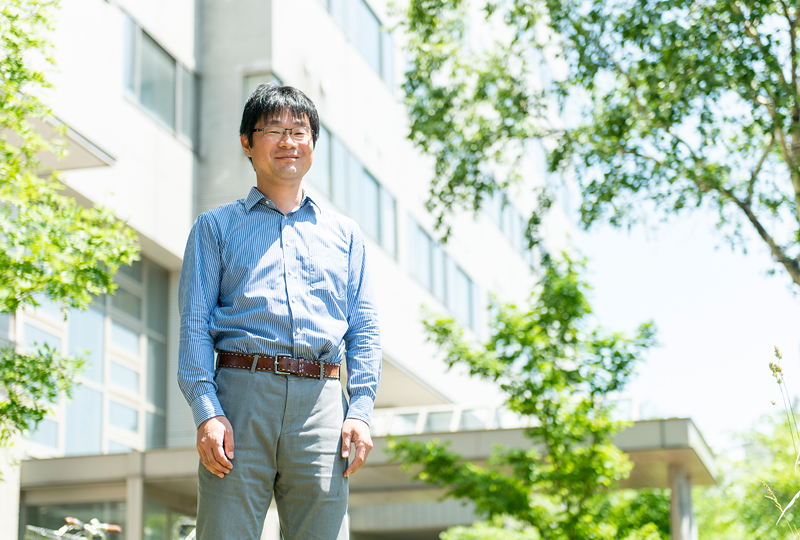
北海道大学 大学院情報科学研究院 調和系工学研究室 教授 川村 秀憲
かわむら・ひでのり
2000年北海道大学大学院博士後期課程修了。同大学助手、准教授を経て2016年同大学教授。2007年〜2008年、日本学術振興会海外特別研究員、ミシガン大学客員研究員。2017年6月より産学官の組織「札幌AIラボ」の座長に就任。釧路市出身。
―研究室の特徴を教えていただけますか?
ディープラーニング、ニューラルネットワークなどの技術をもとに、AIを活用するさまざまな研究を行っています。企業との共同研究の数が北海道大学内でトップクラスであり、企業が直面する課題やニーズに対して、AIをどのように活用していくかが研究のテーマになっています。研究成果から(株)調和技研のようなベンチャー企業も誕生していて、卒業生は幅広い分野で活躍しています。
AIはハサミと同じ。大切なのは「どう使うか」
北大にしかない名称の研究室だと思います。AIは、例えるなら「ハサミ」のように、使い方次第で便利なものにもなれば、危険なものにもなり得ます。この研究室では技術としてのAIを研究するだけでなく、「どう使うか」まで踏み込んで考えることを重視していて、技術を活用した先にある“社会と人との調和”を目指すという思いから「調和系」という名前が付けられているんです。
―研究事例を紹介していただけますか?
最近の事例には、AIで川柳を作るプログラムの開発があります。札幌AIラボのプロジェクトにもなっていた「AI俳句」を発展させたもので、NHKのニュース番組で、その日に話題となった言葉をお題に川柳を詠むAIレポーター・川柳ヨミ子の頭脳に私たちの技術が活用されています。
そのほか、公営ギャンブルである競輪の予想をするAIの研究に運営会社と共同で取り組み、過去のレース結果や選手情報を学習させ、期待値の高い車券を予想するというプログラムを開発。この予想AIはすでに実用化され、Webサイトから誰でも見ることができます。
-
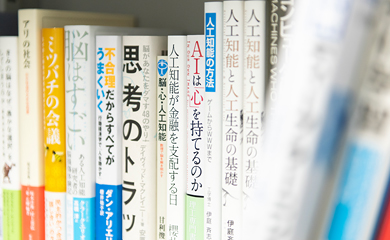
川村教授が率いる調和系工学研究室では、人工知能を実現する上で重要な技術の研究と社会システムへの応用、具体的なサービス開発に取り組んでいる。
-

毎週月曜〜金曜 午後4時50分から放送中の「ニュース シブ5時」に登場する川柳ヨミ子。その日の話題を川柳で披露する。(資料提供=NHK)
-

KDDI総合研究所、はこだて未来大学との共同研究。AIによる学習で人間のような「譲り合い走行」をするRCカーのデモ映像。
現実的な課題に向き合うからこそチャレンジングな研究が可能
ファッション業界のマーケティングにAIを活用するという研究を行いました。ファッションに詳しい女性たちにアイテムごとの印象を「かわいい」「ガーリー」「“とろみ”がある」などのラベル付けをしてもらい、それをディープラーニングで学習させ、AIがアイテムの特徴を数値化できるようにする、というものです。
―ファッションの「ものさし」をAIで作るということでしょうか?
その通りです。ただ通常、AIによる画像認識を行う時は、ひとつの物に対してラベルが明確であることが前提です。鉛筆は「鉛筆」、カメラは「カメラ」といったように。一方、洋服が「かわいい」かどうかは、個人の“見方”にも依存します。一般的な研究室であれば、こうしたものを研究テーマに選ぶことは少ないと思います。
しかし、企業と共同研究を行うと、ニーズに対してどのようにAIを活用するかという視点になるので、いわゆる研究室的なセオリーにとらわれないチャレンジングな研究に取り組むことも多いんです。実際にこの研究では、AIがファッションに詳しい女性と同程度の判定ができるようになり、そういう意味でも、とても印象深い事例となりました。
ディープラーニングの技術が発達し、AIの時代が来ると言われていますが、実際に「使えるレベル」にするには、課題を整理して、実験を重ねて、具体的なシステムに組み込むといった、いくつものプロセスが必要です。ただ、それらを一貫してできる企業や研究機関は、まだ多くありません。
そこで札幌AIラボがその機能を担って、1社では実現できないことを産学官の連携で可能にすれば、「AIに強い札幌」というブランドイメージを作ることができます。経験やノウハウの集積も進むでしょう。札幌AIラボが中心になることで、レベルの高い仕事を国内外から請け負うことも可能になるはずです。
博士号を持った研究者が多く活躍する札幌。技術が集積する環境は整っている
AIの分野で博士号を持った研究者が多くいるというのが強みだと思います。また、北海道出身者は地元への愛着が強く、一度は東京に就職しても、再び札幌に帰ってくるケースが多い。その時に受け皿となる企業も増えつつあり、技術が集積しやすい環境は整っていると感じています。
―札幌市のスマートシティを目指す動きも加速しています。
スマートシティ化は世の中にあるさまざまなムダを無くして効率性を高めることであり、AIやIoTを土台にしたまちづくりを進める取り組みです。ただ、個別的に取り組んでいては古い仕組みや価値観が温存されてしまう懸念があり、時には破壊的に取り組むことも必要だと考えています。
だからこそ産学官によるディスカッションが不可欠なのですが、幸い札幌にはみんなで議論を重ねる場も整っています。街をリデザインするという視点に立ち、そのために今、何をするかを考えていかなければなりません。
-

札幌AIラボでは、AI技術をテーマにしたセミナーやワークショップを開催。
-
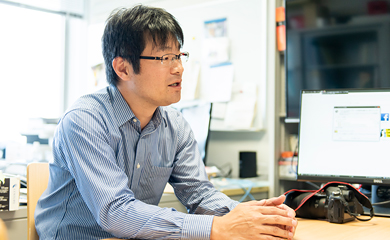
「企業からの依頼は多いですが、学生が論文のテーマにもできるような息の長い案件を選んで共同研究に取り組んでいます」と川村教授。
世界とつながるエコシステムを札幌で
産学官が連携し、世界ともつながるエコシステムが構築できればと考えています。札幌で人材が育ち、新しい技術に取り組み、その技術を使って世界で活躍する。さらに、世界で得た知見を札幌にフィードバックして、また新しい人材が育つ。こうした循環が生まれれば、札幌がもっともっと魅力的な街になると考えています。
北海道大学 大学院情報科学研究院 調和系工学研究室

-
世界で輝きを放つ次世代都市SAPPORO
オープンイノベーションから生まれる、新しい暮らしやすさ
Smart AI City SAPPORO「SAPPORO×IT」
最新記事5件
IT企業の集積と産業振興に力を注ぐ札幌市の取り組み
社員一人ひとりの得意を生かし札幌から新技術を発信する
「遊び心」を大切に、世界に通じるコンテンツを
データ×AI×マーケティングで、札幌にイノベーションを起こしたい
札幌らしいデータ活用で世界とつながる魅力的な都市に


