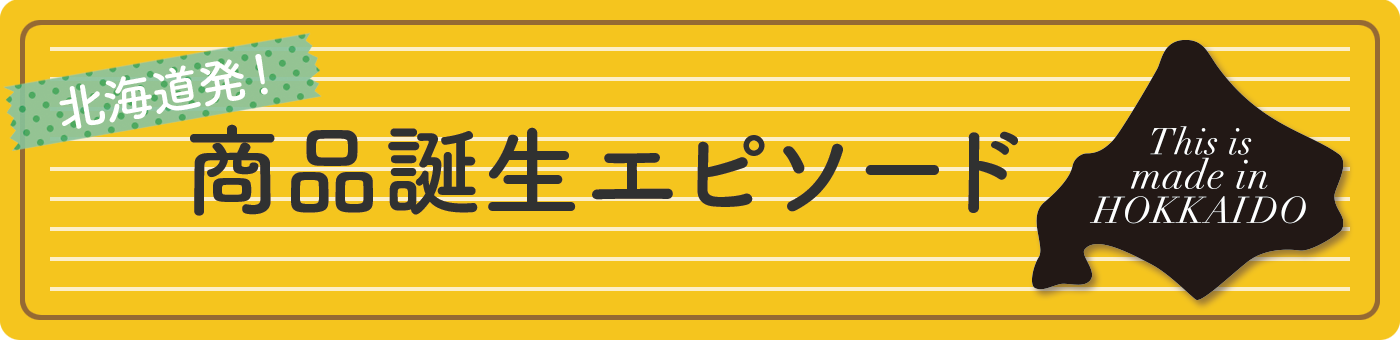 北海道発!商品誕生エピソード【シンプル・イズ・ベストな塩辛!社長のいか塩辛/株式会社布目(函館市)】
北海道発!商品誕生エピソード【シンプル・イズ・ベストな塩辛!社長のいか塩辛/株式会社布目(函館市)】
2020年3月9日 公開

いかの皮をむいた「白造り」が転機に。

株式会社布目代表取締役社長
石黒義男さん
「50年以上も前のこと、私は夜間高校に通いながら、日中は市場の問屋で働いていました。当時の職場では布目のいかの塩辛も扱っていましたが、ゴロ(内蔵)の色がそのまま出ており、味はピカイチでも見た目がイマイチだったんです。一方、薄いピンクに着色されたものは飛ぶように売れていました」
いかのゴロは個体によって色の濃淡が異り、着色しなければ見た目を均一化できないのは当然なのだとか。さらに、一般には皮をむかずに加工することから、塩辛にした時に黒っぽい色が移ることも避けられないといいます。
「転機は昭和36年でした。先代がいかの皮をむいた胴体の肉を使い、ゴロと塩を加えて熟成させた『塩辛の白造り』を売り出しました。その名の通り着色料を使わずとも白っぽく美しい色に仕上がり、身の柔らかさも画期的だったんです」
この商品をリリースするやいなや、本州を中心に大ヒット。「いかの塩辛といえば布目」という不動の地位を築く礎となりました。
お客様への手土産がヒット商品の原点。
「実は私が個人的に作り始めたのが原点なんです(笑)。年末にお客様から『正月料理に飽きそうだから塩辛を食べたい』というご要望もあり、前浜で朝に獲れたばかりの真いかを無着色で添加物をほとんど使わず塩辛として仕込みました。1回に100㎏ほど作り、取引先を回る際の手土産にしていたわけです」
その特別ないかの塩辛は取引先の間で「おいしい」と大評判。石黒さんは、いつしか工場の冷蔵庫に「社長用の塩辛です。触らないように」と黒マジックで書いたダンボールをストックするようになったそうです。
「ある日、社員から『この塩辛を商品化しては?』というアイデアが飛び出しました。最初は私の顔写真をパッケージに印刷するという案が出ましたが、さすがに恥ずかしいのでNGです(笑)。代わりにイメージキャラのイラストを配し、工場のラインで量産できるようにレシピのアレンジを行いました」
ワンランク上の「極」も贈答用に好評。
「いかの塩辛のおいしさを決めるのは良質な原料と鮮度です。それが崩れてしまうと臭みを取るための処理や日持ちをさせるための保存料が重なり、旨みがどんどん削ぎ落とされてしまいます。何より『いかといえば函館』のイメージを損なう塩辛を作ることなんてできっこありません」
まさにシンプル・イズ・ベストを貫いたいかの塩辛。もちろん、原材料の検査やトレーサビリティシステムといった安全性への確保にも余念はありません。3年ほど前には、北海道産の新鮮で肉質の良い真いかを厳選し、製法からパッケージまでこだわり抜いた「社長のいか塩辛 極」を発売しました。
「いかの塩辛としてはかなり高額ですが、贈答用としてのニーズが高く、お客様からの評判も上々です。今後は普段使いとギフト用の2ルートからおいしさを広めていきたいと思っています」
ここがこだわり!開発のポイント
塩辛に最適な真いかを厳選し、コンピューター制御の「低温蒸気解凍庫」で解凍。鮮度と旨みを保った状態で加工に進むため、味を落とすことなくおいしい商品へ仕上げることができます。
発売から20年以上のロングセラー「社長のいか塩辛」は普段使いに。ワンランク上の「社長のいか塩辛 極」は2個セットの箱入りで2,500円程度と贈答用に人気です。
国際的な食品安全マネジメント「FSSC22000」を導入。さらに、仕入れ先の現地調査を実施した上で、品質や安全性が確かめられた素材だけを添加物や保存料を極力使わずに加工しています。
-

贈答用に人気の「社長のいか塩辛 極」
200gビン/200gビン×2セット -

肉厚の真いかを厳選し、ゴロと調味料を加えて熟成。お酒のつまみにも、ご飯のお供にも相性抜群。まろやかな旨みが楽しめる一品。
-

味付け、熟成の様子。
-

国内外産を問わず原料の細菌検査を実施。安全性が確かなものだけを加工。
-

低温蒸気解凍庫では菌の繁殖も抑えられるとか。
-

パッケージにも描かれているイメージキャラクター。
株式会社布目

北海道発!商品誕生エピソード
最新記事5件
サケの白子を原料としたサプリメント「サケノカムイ」の誕生エピソードや将来像について、取締役・共同創業者の千葉祐輔さんにお話を伺いました。
一昨年に誕生した「金のアマニ」の誕生エピソードや将来像について、同社の有川由紀子さんにお話を伺いました。
商品の誕生の経緯について、同社代表取締役の池田浩輔さんにお話を伺いました。
商品開発の経緯や、お菓子作りへの思いを代表の柴田愛里沙さんに伺いました。
スパイスマニアでありながら、中学生のお子さんを育てるお母さんでもある小杉さんに、商品への熱い思いを伺いました。
