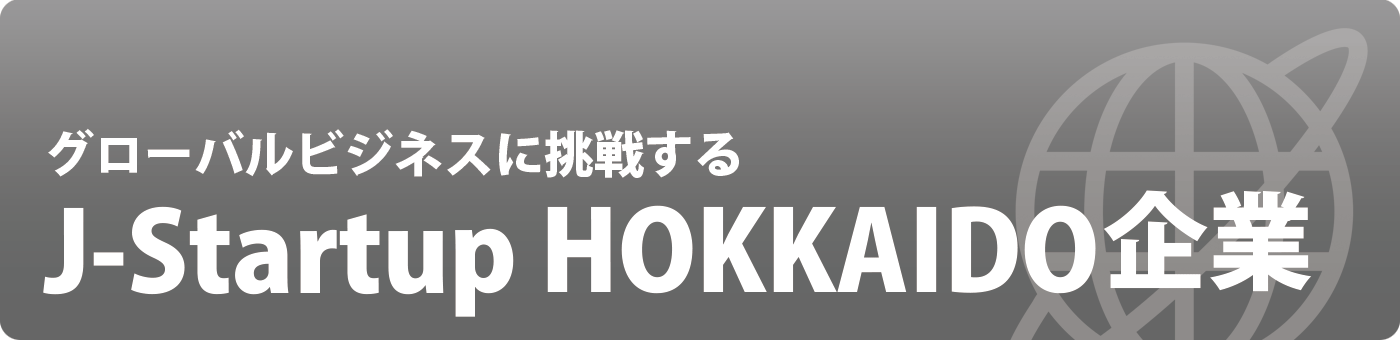 世界中の海難事故から、人々の命と家族の安心を守りたい。【株式会社よびもり】
世界中の海難事故から、人々の命と家族の安心を守りたい。【株式会社よびもり】
2024年6月10日 公開
家族の海難事故が起業のきっかけに。
「『よびもり』はSOSが発信された瞬間から、事故に遭った個人の居場所をGPSを通じて特定します。周囲の漁師や家族がアプリを通じて信号を受信し、すぐに救助に駆け付けられるという仕組みです。これまでも船そのものには遭難信号を発する装置が付いていましたが、個人で使えるものは存在していませんでした。漁業中の転落事故や、小型ボートでの遭難といった悲劇を防ぐために、個人で使えるサービスを作りたいと考えたんです」
誕生するきっかけとなったのが、幼いころに母や祖母から聞いた亡き祖父の話だ。
「僕の祖父は羅臼町の漁師で、漁に出たまま未だに行方不明、遺体も見つかっていないんです。どこで、どのようにして事故に遭ったのかもわかりません」
実は海難事故で人が行方不明になった場合は最大で7年間、死亡認定が下りず、その間家族は保険金をもらうこともできない。精神的なつらさと同時に、経済的にも救いのないまま取り残されることになるのだと、千葉さんは話す。
「当時は母が生まれて間もないころで、祖母は経済的にもとても苦労したそうです。何年たっても『祖父は生きているかもしれない』と話す祖母や母を見て育ったからこそ、同じ思いを誰にもしてほしくない。この問題に取り組むのは、自分の使命だと思い至ったんです」
資金を使い果たした末に製品が完成。
「試作品すら無い状況ですので、〝机上の空論〟ですからね。実体のないものにお金を貸してくれる人がいるのだろうかという懸念があったんです。そこで、目標額に達するまで家に帰らないという決意で東京行きの片道切符を買い、投資家の方々へプレゼン。無謀としか思えない方法で資金集めをしました(笑)。その結果、熱意が届き2週間ほどで目標金額に達成し、ホッとしたのを覚えています」
お金の心配がなくなったのも束の間、今度は発信機の開発に頭を悩ませることになる。ゼロから製品を作ろうとしていた千葉さんたちは、基盤作り、バッテリーの種類、外装の素材や防水度合いなど、その組み合わせが無限大にあるという現実を前に途方に暮れた。
「ベストな組み合わせにたどり着いたとしても、完成品はたったの1個。これを大量生産することができなければ、ビジネスを形にすることはできません。試行錯誤を繰り返し、集めた資金が底を尽きかけたころ、ようやく既存の発信機を使えばいいんだということに気が付き、製品が誕生しました」
世界中の海難事故を限りなくゼロにしたい。
「船で沖に出てライフジャケットを着て海に飛び込み、乗ってきた船には岸に戻ってもらい試験をしたんです。よびもりの発信ボタンを押してから、救助が来るまでの間、水平線を見つめながら漂うだけ。言葉には言い表せないほどの恐怖と絶望感でいっぱいでした」
千葉さんにとっては永遠とも感じられるほどの長い20分。しかし、人の命を救うには充分な早さだと判断した。船が千葉さんの元へ来た時が、製品が本当の意味で完成した瞬間だった。
「海難事故が起きる可能性は漁業関係者でなくとも、どんな方でもありえます。個人で船釣りをする人や、観光船の乗客の方々、湖や川でのアクティビティを楽しむ方など、水に出るすべての人に『よびもり』を携帯してほしいと願いました」
現在は創業の地である福岡市の漁業組合の他、北海道漁業協同組合連合会や羅臼町など北海道の自治体や漁業組合もサービスを導入。2022年に痛ましい海難事故が起きたことを契機に、知床羅臼観光船協議会など観光業界にもサービスが波及しつつある。更に、2023年には需要を見越して北海道に本社を移転。福岡との2拠点でサービスの普及に取り組んでいる。
「南北を拠点に、いずれは日本全国に『よびもり』を普及させていきたいと考えています。既にサービスを通じて救助された方の実例も出てきています。電波の国際法上の問題や通信エリアが海に広がっているかなど、さまざまな課題もクリアできれば、将来的には世界でも利用ができるかもしれません。世界中の海難事故から当事者とその家族を守りたい。その僕らの思いに共感してくれる仲間を一人でも増やし続けることが、これからの目標です」
株式会社よびもり
https://yobimori.com
- 前のページへ
- 次のページへ
グローバルビジネスに挑戦するJ-Startup HOKKAIDO企業
最新記事5件
自らの経験を基に学生起業した千葉佳祐さんに、開発に至った経緯や苦労、今後のビジョンを伺った。
スマホアプリを中心に開発している株式会社インプルの代表、西嶋裕二さんに会社のビジョンを伺った。
灯油の自動発注・配送管理システム「GoNOW」の 開発と提供に取り組む、代表の多田満朗氏に話を伺った。
株式会社調和技研の代表取締役である中村拓哉さんに、これまでの歩みとこれから進んでいく方向についてインタビュー。
酪農・畜産を効率化するクラウド牛群管理システム「Farmnote Color」誕生の経緯や今後の展開について聞きました。




